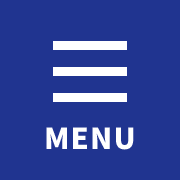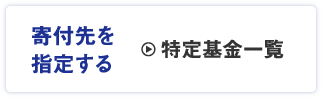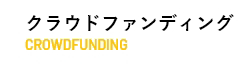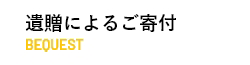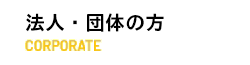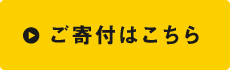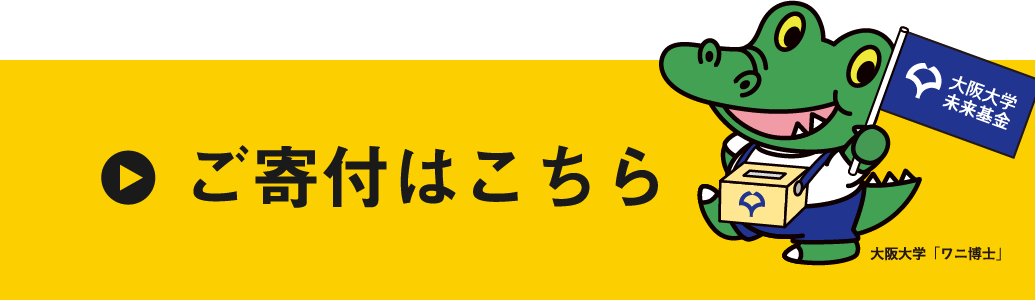総長ロングインタビュー
「地域に生き世界に伸びる」を
次の100年へとつなぐために
2031年に創立100周年を迎える大阪大学は、「地域に生き世界に伸びる」というモットーのもと、
懐徳堂や適塾に根ざした自由闊達な市民精神を基盤に、社会や時代の要請に応じた取り組みを続けてきました。
新しい時代に向けて、変わらないこと、変えていくことを、2025年4月1日に大阪大学第19代総長に就任した熊ノ郷 淳
(くまのごう あつし)にインタビューいたしました。

”自由闊達”とした学風の継承
――総長に就任された感想と決意をお聞かせください。
重要な職責を拝命し、身の引き締まる思いです。本学の精神的源流の一つは、緒方洪庵が開いた適塾です。日本全国から志のある若者たちが集まり、机を並べて静かに教えを受けるのではなく、雑魚寝しながら自由に議論を深め合うような場でした。「さまざまな夢を持った多様な人材が集い、互いに刺激し合って新しい未来を創造する」―これこそが大学のあるべき姿だと考えています。その伝統を継承し、本学の学風である“自由闊達”とした雰囲気のなかで、学生も研究者も思う存分、学問に没頭できる環境にしたいと改めて思っています。実学の精神のもと、学問の府として次代を担う「人」と「知見」を育んでいくことが私の抱負であり使命だと考えています。
直面する問題に対処しつつ、その経験をもとに研究を推進
――本学のモットー「地域に生き世界に伸びる」を実感するエピソードを教えてください。

「地域に生き世界に伸びる」という言葉は、本学第11代総長の山村雄一先生の時代に、本学構成員が一緒になって将来構想委員会を作り、大阪外国語学校(現・大阪大学外国語学部)の卒業生である作家の司馬遼太郎さんの意見も取り入れながらできた言葉だと聞いています。本学はこれをモットーとして、教育研究活動を通じてそれぞれの時代の社会の課題に応えてきました。
身近な例で言うと、2020年に新型コロナウイルス感染症のパンデミックが起きた際、本学医学部附属病院(以下、阪大病院)では地域医療を守るために重症患者の受け入れを行いました。また、全国に先駆けて大学内で地域住民へのワクチン接種を本学構成員が一丸となって実施しました。さらに、大阪が医療崩壊と言われた時期も、阪大病院は大阪府下をはじめ阪神地域の関連病院とのネットワークを活用し、病院間で連携して多くの患者さんに対応することができました。しかし、このことは本学が地域に貢献したということだけのことではありません。その後、本学はこのときに得た検体や臨床情報などのデータをもとに、最新医療の研究を学部を超えて行い、次の世代につなぐ学問的エビデンスとして広く発信するため、世界的にも有名なジャーナルに多くの論文を発表しました。
このような本学の活動に賛同いただいた日本財団から多額の寄付をいただき、次なる感染症の脅威から「いのち」と「くらし」を守るため、2021年4月に「感染症総合教育研究拠点(CiDER)」が設置され、本年2月には感染症の世界的な研究施設となる大阪大学・日本財団感染症センターが竣工しました。
――「実学の阪大」を象徴する医薬品も注目を集めたそうですね。
私の恩師でもある本学第14代総長の岸本忠三先生がサイトカイン「IL-6」を発見したことから、企業との協働によってトシリズマブ(商品名アクテムラ)という抗体薬が開発されました。関節リウマチの治療薬として今でも世界中で使われており、本学発の基礎研究が世界中の患者さんを救う画期的な医薬品の開発につながった、「実学の阪大」の成果として有名です。その抗体薬は新型コロナウイルス感染症肺炎の治療にも有効性がみられ、再び注目を浴びました。
「実学の阪大」を象徴する事例としては、世界初の自動改札システムの実用化も挙げられます。いま大阪・関西万博が行われていますが、凄まじい入場者数だと聞いています。1970年に大阪万博が開催された当時も、地域の人口が急激に膨れ上がりました。そこで、千里ニュータウンの通勤対策と大阪万博の鉄道輸送対策のために、1967年、阪急北千里駅で世界初の自動改札機が実用化されました。これは、本学と鉄道会社、大手電気機器メーカーが共同開発したものになります。
――社会を支える知恵と技術を、どのように育てていけばよいとお考えですか。
大学における学問の在り方そのものを進化させていく必要があると考えます。インターネットがこれだけ普及して、SNSや生成AIなどで何でも調べられる時代なので、大学はもはや知識だけを得る場所ではなくなったと言えるのではないでしょうか。
そこで一つ鍵となるのが、学際的な視野と専門性の両立です。私は「縦糸と横糸の医学」という言葉をよく引用するのですが、縦糸は各分野の専門性の深化を、横糸は分野横断的な広がりを表します。その2つを調和させて織りなすことで、新たな学問領域の創出や社会への貢献が可能になるという考えです。この考え方は医学に限らず、すべての学問に通じます。本学では、各研究者・学生が自らの専門を極めると同時に、他分野の知見を取り入れコラボレーションする文化を育て、知恵と技術の基盤をより豊かで強固なものにしていきたいと思います。
学問の横糸を強化するためには、世の中の移り変わりに柔軟に対応できる力が必要です。産学連携を通して「社会」に触れたり、国内外から招聘した一流の「人」と出会ったりすることで視野が広がり、柔軟性が養われる環境を大学側が提供することが大事だと思っています。「三年学ばんより、三年師を選ぶべし」という言葉があります。「3年遊んでいてもいいから、師となる人を探しなさい」という意味です。一流の人、つまり夢のある人と出会うと、まったく自分が予期していなかったところへ導いてくれる。そんな夢を与えてくれる場所が大学なのではないでしょうか。
――未来を担う若者たちに、どのような社会を手渡していく必要があるでしょうか。
50年後、100年後の社会を思い描くと、AIの発展やグローバル化の深化、気候変動やパンデミックといった課題の顕在化など、いまとは大きく変容した世界かもしれません。しかし、どのような時代であれ、人びとが平和と豊かさを享受し、持続可能な地球を引き継いでいくことができる社会であってほしいと願います。その未来を担う若者たちに手渡す社会をより良いものにするために、大学には大きな責務があります。本学は、「未来を切り拓く力」を生み出し続ける学問の府として、教育と研究を通じて貢献していきます。
寄付を通じた支援が大きな原動力に
――大阪大学にとって「寄付者」というステークホルダーはどのような存在でしょうか。
寄付者の皆様は、本学創設時からの欠かせないパートナーであり、支え手です。本学は、1931年に日本で6番目の帝国大学として設立されましたが、他の帝国大学とは異なり、関西の財界や政界、そして大阪府市民の熱意ある活動の末に創設されたというユニークな歴史を持っています。そのため、その時々の国の政策やトレンドなどに振り回されることなく、国費だけでは賄いきれない先進的な取り組みや、地域に密着した産学連携による研究などを自由に行ってこれたという背景があります。その後も、創設当時、大阪や神戸が外来伝染病の侵入門戸になりつつあったことから微生物病研究所が、そして最近では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの際に、次なる感染症の脅威に備えるため大阪大学・日本財団感染症センターが民間からの寄付によって設立されました。また、免疫学フロンティアセンターも民間からの寄付で運営されています。このように、寄付者の皆様からの支援なくしては成立し得ないのが本学なのです。
――大阪大学未来基金のなかの「ゆめ基金」が充実することによる、社会へのインパクトをどのようにお考えでしょうか。

ご寄付やご寄付を原資にした資金運用による運用益で大学財政の安定性・持続性が高まれば、適塾のように自由闊達とした雰囲気のなかで学問に没頭できるようになります。それはつまり、短期的な成果にとらわれず腰を据えて取り組む基礎研究や、画期的なブレイクスルーにつながるようなチャレンジングな研究にも大胆に資源を投じることができるということです。
これまでに行われた研究で言うと、一つは量子コンピュータです。量子情報・量子生命研究センター長を務める北川勝浩先生が、何十年も前の、世間がまだ「量子って何?」というような時代から続けてこられた研究の成果が、「純国産」量子コンピュータの開発につながっています。もう一つの例が、レーザー科学研究所長の兒玉了祐先生が研究を続けてこられたパワーレーザーです。一時は世界の潮流から外れた時代があるそうですが、持続可能なクリーンエネルギー、なかでもフュージョンエネルギーという分野ができたことで改めて注目を集め、国からも予算がつくようになりました。これらの研究は、寄付金などの資金のもと、本学が自由に研究を続けてこられた成果だと言えます。
そういった大学経営が定着すれば、大学への寄付が社会の発展に直結するという意識が広まり、教育や研究がもはや大学だけのものではなく、社会全体のプロジェクトだという文化の醸成につながります。また資金面の充実は、奨学金制度の拡充にも直結します。経済的な理由で進学を諦めるような若者を一人でも減らし、才能ある人材が経済格差に左右されずに存分に学べる環境を用意するという大学の重要な使命も果たせるでしょう。
次の100年を共に築くために
――寄付者の皆様へメッセージをお願いします。
平素より大阪大学を温かくご支援くださっている皆様に、心より御礼申し上げます。皆様からのご厚意とご支援の一つひとつが本学の教育・研究を力強く後押しし、ひいては社会に新たな価値を生み出す原動力となっています。本学は創設の原点から市民・財界の皆様に支えられてきた大学であり、その「市民精神」を今も受け継いでいます。私たちは、寄付金を学生の学びや研究者の挑戦を支えるために有効活用し、教育・研究の充実した成果として社会に還元してまいります。
大学を取り巻く環境が時代とともに変化するなか、皆様の存在はますます重要になっています。皆様のご支援なしには成し得なかった教育・研究の成果がこれまで数多くあります。その感謝の念を忘れず、皆様と志を共にしながら「地域に生き世界に伸びる」大阪大学をさらに前進させていきたいと思います。次の100年を築くための礎を、共に構築していきましょう。引き続き、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
熊ノ郷 淳(くまのごう あつし)
1966年生まれ、大阪府出身。85年大阪大学医学部に入学。卒業後、内科臨床研修を経て大学院に進学し、医学博士号を取得。2007年大阪大学微生物病研究所教授に就任。08年より世界トップレベル研究拠点(WPI)である大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授を兼任。11年からは大阪大学大学院医学系研究科・呼吸器・免疫内科学教授を務め、医学・免疫学分野における教育・研究に尽力。その後、大阪大学副理事、同大学院医学系研究科長、大阪大学参与を歴任し、25年4月より現職。
●これまでの研究
専門は内科学、免疫学。セマフォリンの免疫系における役割を初めて解明するなど研究成果を重ね、新型コロナウイルスの研究でも最前線に立つ役割を果たす。日本免疫学会賞、大阪科学賞など受賞多数。
●趣味・息抜き
「音楽やお笑いが好きです。音楽は分野を問わずいろいろなものを聴きますし、お笑いは毎年M-1グランプリを楽しみにしていて、放送後の有料配信もチェックします。普段はSNSを見て回ったり、MLBのシーズン中は大谷選手の試合をチェックしたりすることが息抜きになっています」。